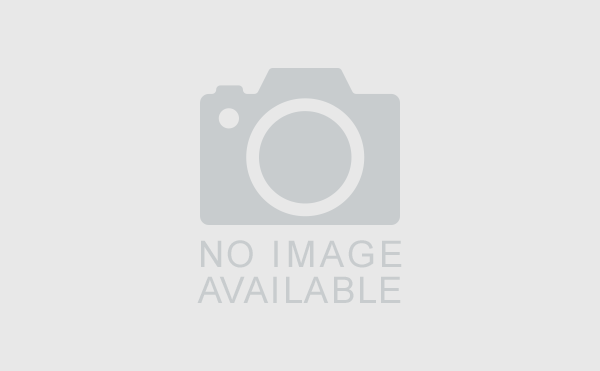“米農家をこれ以上減らさない”本市でも取り組みを
政府は、米価高騰の原因が生産量の不足であることを、ようやく認めました。そして、これまでの減反(生産調整)から、2027年度以降は増産に転換することを明らかにしています。
政府はこの30年間、米の価格や流通に政府は関与しないという「市場まかせ」政策を続けてきました。その結果、生産者米価は低下し続け、60キロ2万円を超えていた価格は、1万円前後まで落ち込み、「米作って飯食えねえ!」という悲痛な声が広がりました。米農家は175万戸から53万戸(24年)に激減し、生産基盤の崩壊という深刻な事態となっています。
米を増産して価格を安定させるためにも、これ以上、米農家を減らすわけにはいきません。米農家にとって重要なことは、米を作っても赤字にならない適性価格で販売できる、ということです。そこで、船橋市としても、市内産のお米を適正価格で買い取り、学校給食で使用することを求めました。
「いすみ方式」を船橋市でも
現在、学校給食で使用されているお米の量は、2023年度で、小・中・特別支援学校を合わせて493トン。このうち、市内産のお米はわずか16トンです。農業センサスのデータ(2020年)では、市内で生産されているお米の量は393トンなので、納入量を増やすことは可能です。
質問では、適正価格で購入して学校給食で使用すること、船橋市の農業基本計画で、学校給食の全量を市内産米で実施することを目標としてかかげるよう要望しました。
 千葉県内には、全国でも有名な、いすみ市の取り組みがあります。「いすみ方式」と呼ばれるこの取り組みでは、学校給食で使用するお米の全量が、市内産の有機米です。 千葉県内には、全国でも有名な、いすみ市の取り組みがあります。「いすみ方式」と呼ばれるこの取り組みでは、学校給食で使用するお米の全量が、市内産の有機米です。
船橋市でも、こうした取り組みができるよう、引き続き、求めていきます。 |


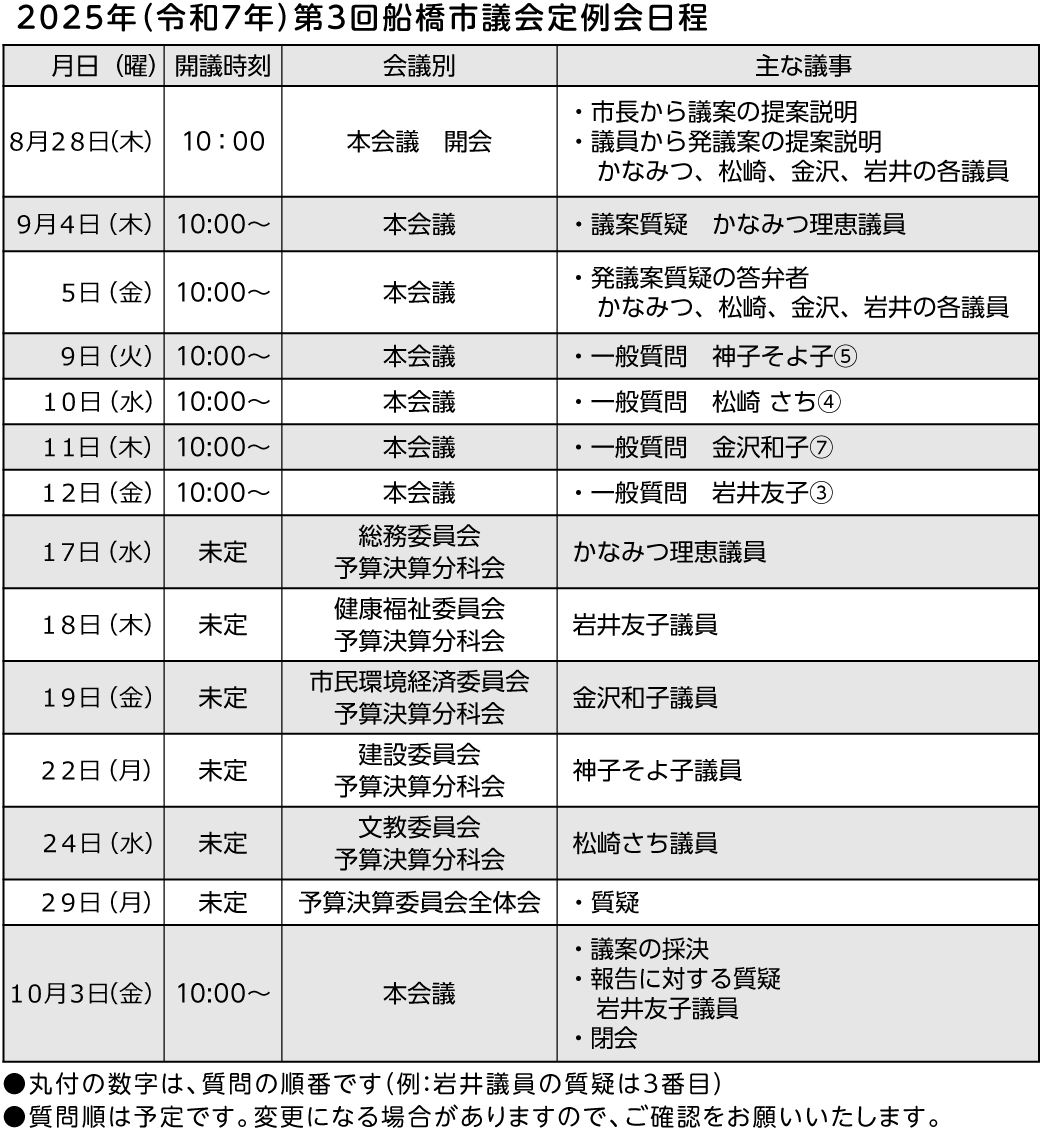
 千葉県内には、全国でも有名な、いすみ市の取り組みがあります。「いすみ方式」と呼ばれるこの取り組みでは、学校給食で使用するお米の全量が、市内産の有機米です。
千葉県内には、全国でも有名な、いすみ市の取り組みがあります。「いすみ方式」と呼ばれるこの取り組みでは、学校給食で使用するお米の全量が、市内産の有機米です。