埋蔵文化財事務所を利用して
新たな「子どもの居場所」の整備を要望
船橋市では24地区すべてに児童ホームを設置するとしていました。しかし、二和・大穴・本町地区には「適当な場所がない」ことを理由に、児童ホームが設置されてきませんでした。日本共産党はこれまで、この3地区への児童ホームの設置を議会でも度々求めてきましたが、2023年に議会で取り上げた際には、「これまでの児童ホームという形ではなく、今後は『子どもの多様な居場所』のあり方について、考えていく」との答弁がありました。
二和東5丁目国家公務員宿舎跡地の解体工事が2025年11月4日から始まりました。国家公務員宿舎跡地活用事業では、防災公園と「児童ホーム」や「老人憩いの家」が設置可能な複合施設を建設するはずですが、新たな複合施設は建設されないことになりました。
三咲小学校近くにある、船橋市埋蔵文化財調査事務所(旧二和公民館)は、手狭になったため、旧金杉台中学校に移転が決まっており、2026年度中に引っ越し完了予定です。
議会で日本共産党は、「乳幼児や小学生だけでなく中学生や高校生、不登校の児童や生徒などにも対応できる、現在のニーズに沿った新たな『子どもの居場所』として、この『埋蔵文化財調査事務所』建物を利用してはどうか」と提案しました。市からは、「今後の『埋蔵文化財調査事務所』建物の利用については、新たな『子どもの居場所』も含め、現在庁内で検討中」との答弁が得られました。
二和地区の新たな「子どもの居場所」の実現に向け、引き続き取り組みます。
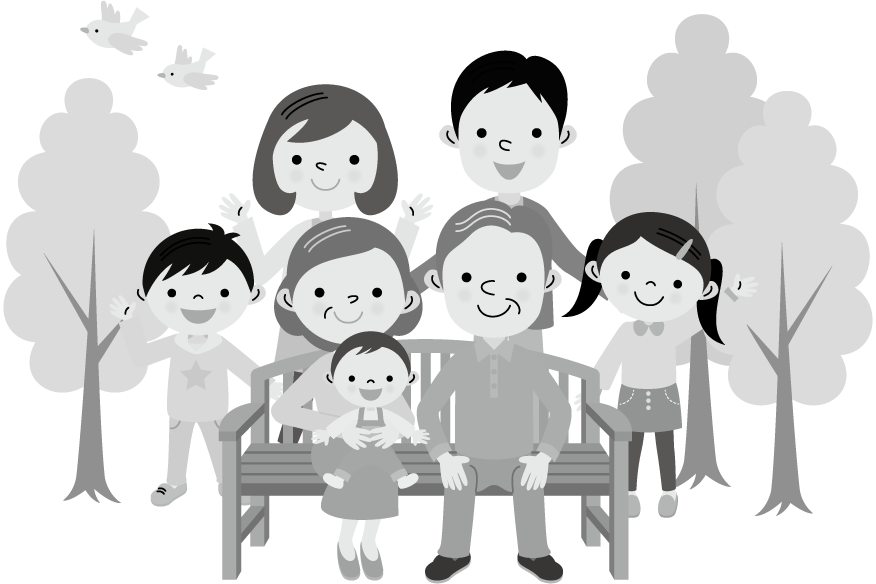
|